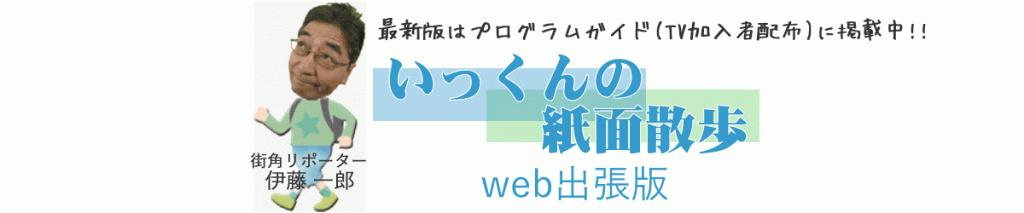
俳優の山崎努さんによると、能・狂言・歌舞伎などの古典芸能を演ずる人を「役者」と呼び、それ以外の演者を「俳優」という。
このところ映画館にでかけることが多くなった。見ごたえのある作品が続いている。「拳と祈り(袴田巖の生涯)」「敵(筒井康隆・原作)」「名もなき者(ボブ・ディラン)」「オッペンハイマー」「教皇選挙(コンクラーベ)」「国宝」などなど。まだまだ観たい作品がある。できるだけパンフレットを手に入れて、制作の背景などの知識を補って、鑑賞の余韻に浸っている。
中でも歌舞伎界を描いた「国宝」に、驚いた。昨年、初めて歌舞伎座に出かけて、玉三郎、染五郎の演技に圧倒されたばかりの私には、この映画は奇跡のような出来事だった。「名もなき者」のボブ・ディラン役にも目を見張ったが、この映画の俳優陣の技量には舌を巻いた。鬼気迫るとはこのこと。「俳優が役者になった」、こう書くと妙に思われるかも知れないが、山崎努さんの区分けに随ってみた。
発見があった。「女形(おんながた)」は昔から歌舞伎界特有のものだと信じていたが、パンフレットによると、演劇の発祥以来、つまり紀元前のギリシャ劇や、シェイクスピア劇、中国の京劇など、全世界で女性役は全て男性が演じていた、という。
女優は17世紀の世界の演劇シーンにはまだ定着しておらず、定着し始めたのは18世紀以降とのこと。「女形」を継続しているのは歌舞伎だけで、特異な文化遺産である、という解説だった。
ちなみに、ねぶた師さんには歌舞伎ファンが多い。「歌舞伎座の楽屋に気兼ねなく出入りできて、役者さんに挨拶できるようになれたらいいなぁ」とおっしゃる方がいた。これは不意打ちだった。言われてみれば、歌舞伎の題材が多いねぶた文化の発信源のひとつとして、役者さんたちとの交流から、何かしらが大きく変わっていくような気がする。手始めに、祭りに役者さんをお招きしてはどうか。

