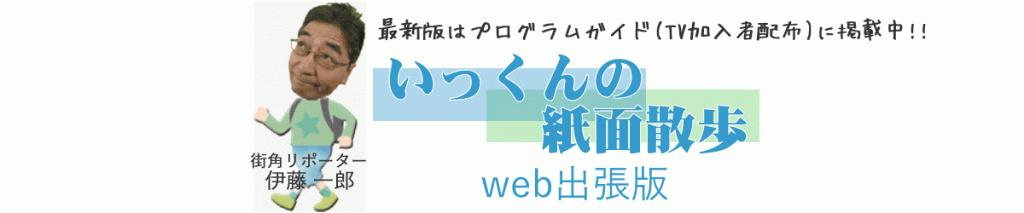
年に一度の楽しみは「旅」である。そのため、無理のない程度にせっせと倹約に努めている。旅はいい。人物に限らない、「押し活」は滋養になる。生きがい、うるおいだ。
大相撲九月場所の千秋楽。私は、国技館の向正面・升席にいた。中入り前の十両戦の終盤には、青森の新星・尊富士関の登場だ。国技館名物の焼き鳥を頬張り、缶ビールを一口含む。足元の紙袋には、購入したポストカード・巾着・ミニ「すもうのぼり」が入っている。全部、尊富士関連だ。声援が沸き上がった。私は土俵に向けて尊富士の名入りTシャツを掲げた。
スマホのカメラを向けてすぐ、電車道で、尊ちゃんが勝ち名乗りを受けた。「もうちょっと、ゆっくりやってよ」。速攻相撲だから仕方がない。それにしても強すぎる。胸がすく。
初めての国技館である。それも千秋楽だ。君が代斉唱や、賜杯を受けたあとには優勝力士のインタビューがある。遠く向こう側には、「NHKの放送席」が見えていた。国技館の入り口で、取り組み表の載ったパンフレットをもらう。パンフには、審判名、時々の呼び出し名と行司名、またご丁寧にも「懸賞」のスポンサーの内訳などが事細かに紹介されている。そして大団円。千秋楽の締めは、手打ち式と、神送りの儀式へと続く。
ナマはやはり、テレビ画面で見慣れた光景とは様子が異なった。祭りである。咲き誇る桜花、爛漫の観客の中心にひときわ明るい土俵がある。空気はひとつ、観客はみんな一期一会の同好の士だ。そして驚いたことに、升席の後ろにはテーブル付きのさらに特等席があった。
さて実は。その前日、こちらもお初の歌舞伎座にいた。まず開演前の、入れ替わる四枚もの緞帳に驚いた。演目は、坂東玉三郎・尾上松緑の「妹背山(いもせやま)」と、松本幸四郎の「勧進帳」だった。ツアー用の特等席を得たが、上には上があって、客席の上手下手にはテーブル付きのさらに特上席があった。聞いてなかった。世上は、想像していたよりひと廻り「豊か」である。

